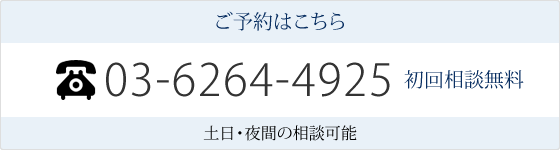事例でみる不動産相続4~見るべき資産が戸建住宅のみの場合~
2016.03.29更新
前回の続きで,相続財産は時価3000万円の自宅不動産のみで,家を出ている次男から自宅に住んでいた長男に対し,自宅を売却し,その半分を自分に渡すべきだ,渡せないのであれば自宅の時価3000万円の半分である1500万円を払えと言われてしまった事案の解決についてご紹介します。
自宅の評価額については,次男の弁護士は,不動産業者の査定額として時価3000万円という金額を提示してきましたが,不動産業者の査定額は,実際に売却できる金額よりも高値であることが多いのです。こちらは不動産評価の専門家である不動産鑑定士の鑑定を依頼したところ,評価額は2000万円となりました。
そのため,寄与分と評価額での主張を行ったところ,最終的には長男から次男に対して600万円を支払うことで決着することとなりました。次男が依頼した弁護士の当初提示案である1500万円から900万円ほど下げての解決となったのです。
投稿者: