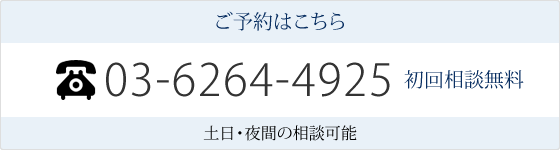検認手続は,法定相続人等の戸籍謄本などを用意して、相続開始地である遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は、相続人や利害関係者を立ち会わせたうえで、遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査して調書を作成し,検認手続きが終了したときは,申立人に対して検認済証明書を付した遺言を返還し,検認に立ち会わなかった申立人や利害関係者には遺言を検認した旨を通知します。
検認手続は、遺言の有効無効を判断するものではないので、検認を受けなくても遺言が無効になることはありませんが,家庭裁判所で検認手続をしなかった人は5万円以下の過料に処せられることもありますので,注意が必要です。また,検認手続が行わないと遺された自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえませんので,登記実務では公正証書以外の遺言は検認が必要とされています。
遺言者が書いたものではない、自由な意思で書いたものではない等の理由で遺言の無効を主張する場合は,検認手続ではなく,別の訴訟手続きを行う必要があります。